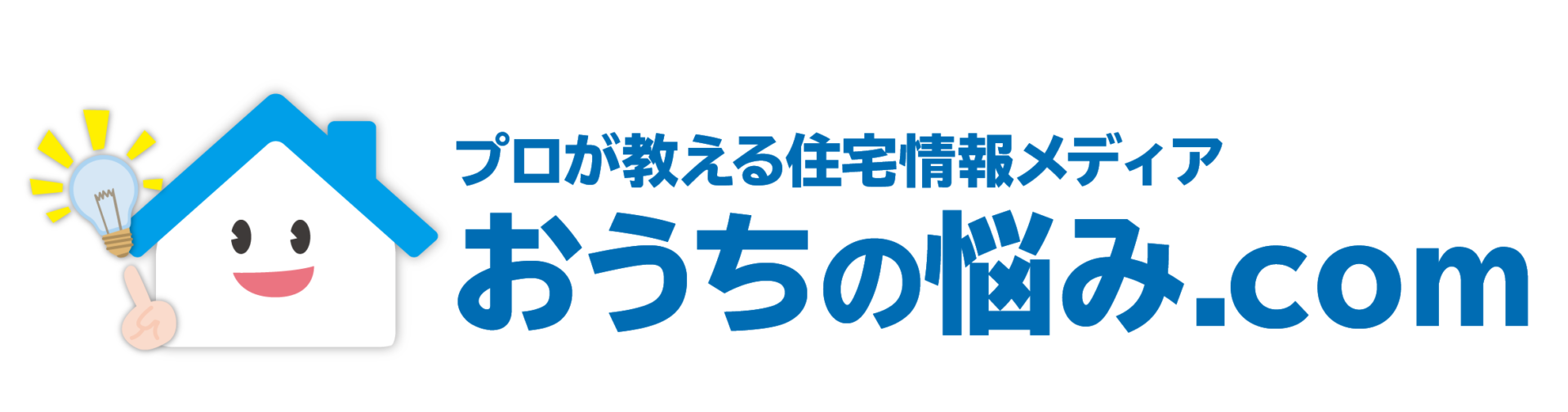住宅の購入を検討し始めると、さまざまな減税措置や補助金などの制度がありますよね。
できるだけ負担を減らすために、受けられる制度があれば有効に活用したいものです。
しかし、色々な制度があり、自分に合う減税がどれかわからず、難しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
『住宅ローン減税』は知っている方も多いと思いますが、今回は『投資型減税』について解説します。
基本的な概要から、併用して受けられる制度なども紹介しますので、最後までご覧ください。
投資型減税とは

投資型減税とは、住宅ローンを利用せず、自己資金のみで一定のレベル以上の省エネ住宅(認定長期優良住宅または認定低炭素住宅)を購入する人向けの制度です。
住宅ローンを利用する人は、『住宅ローン減税』という制度を利用して減税することができますが、住宅ローンを利用せず自己資金のみで住宅を購入する方は『住宅ローン減税』を利用できません。
住宅ローンの利用の有無によって受けられる恩恵に違いがあると、少々不公平に感じてしまいますよね。
投資型減税とは、そんな不公平感を軽減するために導入された制度です。
また、新築の際に適用となるほか、リフォーム費用に対しても適用となる場合もあります。
まとめると、下の表の通りです。
| ローン利用 | 住宅ローン減税 | 投資型減税 | |
| 一定レベル以上の省エネ住宅 | あり | ◯ | ◯※ |
| なし | × | ◯ | |
| 一般的な住宅 | あり | ◯ | × |
| なし | × | × |
※投資型減税と住宅ローン減税を同時に受けることはできません。
認定長期優良住宅と認定低炭素住宅とは
投資型減税を受けるための要件である、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅とはどのような住宅なのでしょうか。
認定長期優良住宅とは、長く良い状態で住むことができる住宅であると認定された住宅のことです。
認定の基準として、劣化対策や省エネルギー性、居住環境への配慮などが設けられています。
詳しくは国土交通省のウェブサイトで確認してください。
[surfing_su_note_ex note_color=”#f5f5f5″]参考:国土交通省ウェブサイト「長期優良住宅のページ」
[/surfing_su_note_ex]長期優良住宅の認定を受けたうえで、一定の条件を満たすことで投資型減税の他にもさまざまなメリットを受けることができます。
認定低炭素住宅とは、居住することで発生する二酸化炭素を抑制すると認定された住宅のことで、
[surfing_su_note_ex note_color=”#F8F8FF”]- 省エネルギー基準の一次エネルギー消費量の10%を超える省エネ性能を有すること
- 選択的項目の2つ以上に該当すること
をクリアする必要があります。
ひとつめは一見難しそうですが、要するに省エネに関するある基準を超えれば大丈夫ということです。
[surfing_voice icon=”https://outinonayami.com/wp-content/uploads/2022/04/-scaled-e1650018559774.jpg” name=”佐藤” type=”l” bg_color=”eee” font_color=”000″ border_color=”eee”]『ある基準』とは20年以上前に設定されたもので、現在はその10%を超えることはそれほど難しくないと言われています。[/surfing_voice]ふたつめは、節水対策やエネルギーマネジメントなど8つの項目のうち2つ以上に該当すればクリア。
具体的には、食器洗い機の設置や太陽光発電設備と蓄電池を設置することなどで該当となりますので、少し意識すればクリアできそうですね。
詳細は国土交通省のウェブサイトで確認しましょう。
[surfing_su_note_ex note_color=”#f5f5f5″]参考:国土交通省ウェブサイト「低炭素建築物認定制度 関連情報」
[/surfing_su_note_ex]
投資型減税の控除期間と限度額
投資型減税の控除期間は1年間です。
住宅ローン減税のように長い期間ではありませんので注意してくださいね。
投資型減税の控除額はその年に納めた所得税から控除しますが、控除しきれなかった場合は翌年の所得税から控除されます。

また、投資型減税の限度額は65万円。
誰でも必ず65万円が控除されるということではありませんので注意が必要です。
下の式によって計算された金額が65万円を超えている場合の控除額は、上限の65万円になってしまいます。
[surfing_su_note_ex note_color=”#F8F8FF”]控除額=性能強化費用相当額×10%
[/surfing_su_note_ex]例えば、性能強化費用相当額が700万円だとした場合、上記の計算式に当てはめると70万円という結果になりますが、控除されるのは上限額である65万円になります。
床面積が149㎡以上の建物は、上限額の65万円の控除が可能ということになりますね。
性能強化費用相当額とは、省エネ住宅とするために一般的な住宅よりも多くかかる費用のことで、住宅の構造区分に関わらず以下の式で計算します。
[surfing_su_note_ex note_color=”#F8F8FF”]性能強化費用相当額=床面積×45,300円※
[/surfing_su_note_ex]※令和2年1月1日から令和3年12月31日までに居住を開始した場合。
平成26年4月1日から令和元年12月31日までに居住を開始した場合は43,800円
リフォーム型投資型減税の控除期間と限度額
リフォームの費用に対して受けられる投資型減税は、リフォームの内容によってそれぞれ控除額が異なる場合があります。
投資型減税の対象となるリフォーム内容と控除額は、下の表の通りです。
| 工事内容 | 対象 | 控除期間 | 控除対象
限度額 |
上限額(10%) |
| 耐震リフォーム | 所得税 | 1年※1 | 250万円 | 25万円 |
| バリアフリー
リフォーム |
1年
(改修後、居住を開始した年分) |
200万円 | 20万円 | |
| 省エネ
リフォーム |
250万円
※2 |
25万円
(35万円) |
||
| 同居対応
リフォーム |
250万円 | 25万円 | ||
| 長期優良住宅化
リフォーム |
250万円
※3 |
25万円
(50万円) |
参考:一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会ホームページ「住宅リフォームの支援制度」
※1 改修工事を完了した日の属する年分
※2 太陽光発電併用で350万円
※3 耐震+省エネ+耐久性向上の場合500万円
リフォーム型の場合は、新築の場合に比べて控除額が少額であることが分かりますね。
自分のリフォームが、どの工事内容に該当するのか事前に確認しましょう。
投資型減税の適用条件
投資型減税の適用条件は、新築の場合とリフォーム型の場合で違います。
さらに、リフォーム型の中でも工事の種類によって適用条件が異なるので注意が必要です。
自分が受けられる減税はどのケースなのかを確認しましょう。
新築の場合の適用条件
新築の場合の、主な適用条件は以下のとおりです。
[surfing_su_note_ex note_color=”#F8F8FF”]- 認定住宅の新築または建築後使用されたことのない認定住宅であること
- 新築または取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
- この税額控除を受ける年分の合計所得の金額が3,000万円以下であること
- 新築または取得をした住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上が自己の居住の用に供するものであること
出典:国税庁ホームページ
1つめの条件は『認定住宅の新築または建築後使用されたことのない認定住宅であること』です。
『認定住宅』とは、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅のこと。
認定住宅でも、過去に誰かが使用したことがある中古物件では条件を満たすことができません。
2つの条件は『新築または取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供していること』。
この条件により普段は住んでいないセカンドハウスや、人に貸す目的の賃貸物件が適用外であると考えられます。
もし自分で住むとしても、引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住しなければなりません。
3つめの『この税額控除を受ける年分の合計所得の金額が3,000万円以下であること』では、適用外になる方は少ないかもしれませんね。
しかし、もし共同で家を所有する場合は、その所有者の所得の合計が対象であるため注意が必要。
例えば、夫婦で共有する場合は2人の所得の合計金額が3,000万円以下であることが条件となります。
4つめは、『新築または取得をした住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上が自己の居住の用に供するものであること』です。
お店や事務所などを併用している住宅の場合は、居住している面積が建物全体の2分の1でなければいけません。
面積に関して特に注意したいのがマンションの場合です。
マンションの場合は『内法面積』が50㎡以上なければいけません。
よく不動産会社の広告などでみる面積は、壁の中心線から測った『壁芯面積』で記載されていることがほとんど。
内法面積は、全部事項証明書で確認することができますよ。
リフォームの場合の適用条件
リフォーム型投資型減税の、主な適用条件を紹介します。
適用条件は、行うリフォーム工事の種類によって違いがありますので注意が必要です。
| リフォームの種類 | 主な適用条件 |
| 耐震リフォーム | 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること |
| 自ら居住する住宅であること | |
| 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること | |
| バリアフリー
リフォーム |
バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること |
| 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の2分の1以上であること(併用住宅の場合) | |
| ①〜④(※)のいずれかが自ら所有し、居住する住宅であること | |
| 新築された日から10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅を除く) | |
| 省エネリフォーム | 省エネ改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること |
| 省エネ改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること | |
| 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の2分の1であること | |
| 同居対応リフォーム | 対象となる同居対応改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること |
| 改修工事後、その者の居住用の部分に調理室、浴室、便所または玄関のうち、いずれか2以上の室がそれぞれ複数あること | |
| 長期優良住宅化
リフォーム |
一定の耐震改修または一定の省エネ改修工事と併せて行うこと |
| 増改築による長期優良住宅の認定を受けていること | |
| 行った改修についての標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること |
※①50歳以上の者 ②要介護または要支援の認定を受けている者 ③障がい者
④65歳以上の親族または、②もしくは③に該当する親族のいずれかと同居している者
参考:一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会ホームページ「住宅リフォームの支援制度」
[/surfing_su_note_ex]
投資型減税の申請方法
投資型減税の申請に必要な、主な書類を表にまとめました。
新築の場合と、リフォーム型の場合で提出する書類が違いますので注意しましょう。
また、自分で提出書類の準備が難しい場合は、建築士や指定確認検査機関などに依頼するとスムーズです。
| 主な必要書類 | |
| 新築の場合 | 控除額の計算に必要な明細書 |
| 登記事項証明書 | |
| 請負契約書または売買契約書 | |
| 長期優良住宅認定通知書 | |
| 住宅用家屋証明書または認定長期優良住宅建築証明書 | |
| リフォーム型の場合 | 増改築等工事証明書 |
| 住宅耐震改修証明書(耐震のみ) |
申請は、いずれも入居日の翌年の確定申告の時期に行います。
必要書類の中には、手配に時間がかかるものもあるかもしれませんので、余裕を持って準備しておきましょう。
提出先は、新築の場合もリフォーム型の場合も、お住まいの地域を管轄する税務署です。
投資型減税は住宅ローン減税と併用できない

投資型減税と住宅ローン減税は、併用して受けることはできません。
両方の制度を同時に受けられるようにしてしまうと、住宅ローンの利用による不公平感を拭うことができないからです。
住宅を購入する際、多くの人は住宅ローンを利用するため住宅ローン減税を受けることができますよね。
一方、投資型減税は現金で住宅を購入した人でも、減税の恩恵を受けられるようにと用意された制度です。
不公平感を無くすために用意された投資型減税を、住宅ローン利用者も同時に受けられたら不公平感が残ってしまうことになります。
ちなみに、住宅ローンを利用している人でも、住宅ローン減税ではなく投資型減税を受けることを選ぶこともできますので覚えておきましょう。
| 住宅ローン減税 | 投資型減税 | |
| 住宅ローンで購入(※) | ◯ | ◯ |
| 現金で購入 | × | ◯ |
※どちらかひとつだけ受けられる
また、居住を開始した年とその前後2年間(計5年間)は、譲渡所得税に関する3,000万円の特別控除や特定居住用財産の買換え特例なども併用できませんので注意が必要です。
投資型減税と住宅ローン減税を比較!
投資型減税と住宅ローン減税は併用することができません。
では、住宅ローンを利用して認定長期優良住宅または認定低炭素住宅を購入する場合、どちらの減税を受けるべきなのでしょうか?
ここでは、投資型減税と住宅ローンそれぞれの詳細を比較します。
| 住宅ローン減税(※) | 投資型減税 | |
| 控除対象限度額 | 5,000万円 | 650万円 |
| 控除期間 | 10年間 | 1年 |
| 控除率 | 1% | 10% |
| 最大控除額 | 500万円 | 65万円 |
※低炭素住宅または長期優良住宅の場合
控除対象限度額はそれぞれ表のとおりです。
住宅ローン減税は残っている住宅ローンの金額が対象となります。
投資型減税は、下の計算式によって控除対象限度額を算出できます。
[surfing_su_note_ex note_color=”#F8F8FF”]控除額=性能強化費用相当額×10%
[/surfing_su_note_ex]※性能強化費用相当額とは、省エネ住宅とするために一般的な住宅よりも多くかかる費用のこと。
令和2年1月1日以降に住み始めた場合は、住宅の構造に関わらず以下の式で計算します。
[surfing_su_note_ex note_color=”#F8F8FF”]性能強化費用相当額=床面積×45,300円
[/surfing_su_note_ex]
また、住宅ローン減税の控除期間は10年間と長期で受けられることがわかりますね。
例えば、控除対象額が限度額の5,000万円だった場合、控除率1%をかけて1年で50万円の減税となります。
それを10年間受けることができるので、最大控除額は500万円となる訳です。
一方、投資型減税は1年間しか受けることができません。
控除率は10%ですが、対象限度額が650万円のため最大控除額は65万円となります。
こうして比べてみると、両方の減税を受けられる人は住宅ローン減税を選んだ方がいいかもしれませんね。
投資型減税は、国が推奨する「いい家に長く住む」という方向性に貢献しているのに、住宅ローンを利用しなかっただけで減税を受けられない人のための救済措置と言えるかもしれません。
すまい給付金と併用できる条件とは?

投資型減税とすまい給付金は同時に受けることができます。
ここでは、両方の制度を受けられる条件について解説しますので、ご覧ください。
すまい給付金とは、消費税引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために作られた制度のこと。
住宅ローン減税は所得税から控除する仕組みのため、収入が低いほどどうしてもその効果が小さくなってしまいます。
すまい給付金は、そんな住宅ローン減税の効果を十分に受けられない収入層のために作られた制度です。
一方、投資型減税は住宅ローン減税を利用している人との不公平感を軽減するために作られた制度でしたよね。
背景が違う制度のため、両方の恩恵を併用して受けることができるという訳です。
ただしすまい給付金は、収入が一定以下の人しか対象となりませんので注意しましょう。
加えて、住宅ローンを利用しない場合は年齢が50歳以上であることも要件となりますので覚えておきましょう。
参考:国土交通省「すまい給付金サイト」
まとめ
今回は投資型減税について解説しました。
住宅を現金で購入する人向けの制度のため、もしかしたら該当する人は少ないかもしれません。
しかし、住宅の購入は決して安い買い物ではありませんよね。
受けられる減税措置はしっかりと受けることで、家計の負担を減らすことができます。
今回紹介したような減税措置は、年々更新されますので関係する期間のホームページなどで最新の情報を確認しましょう!
[surfing_su_note_ex note_color=”#F8F8FF”]
▶︎次の記事
[/surfing_su_note_ex]