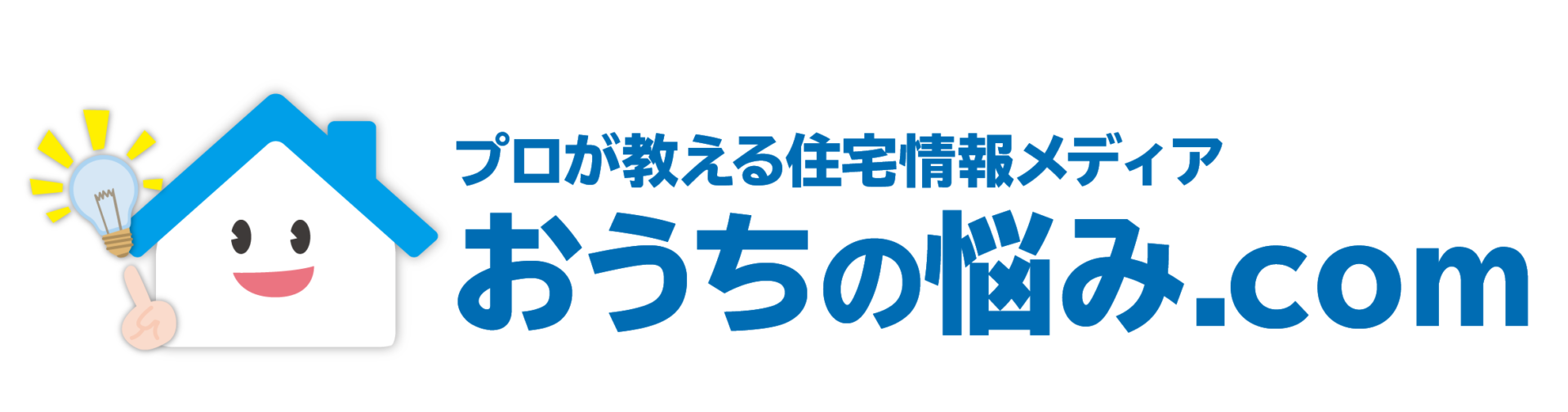自宅の太陽光発電を使い始めて10年経つと『卒FIT』を迎えることになります。
「売電収入がなくなる」と不安な方も多いのではないでしょうか。
今回は、
- 卒FITとは
- 卒FIT後、何もしないとどうなるのか
- 余った電気はどうするのがベストなのか
について、2012年に太陽光発電を使い始めて2022年には卒FITを迎える私のケースでシミュレーションした結果も交えて紹介します。
「これまで特に何もせずにきたし、これからも何もしなくても大丈夫」と思っていると、電気料金が大きく家計を圧迫することになるかもしれません!
FIT期間満了時に慌てないためにも、今から準備を始めましょう。
卒FITとは
『卒FIT』がどういった状態を指すのかを詳しく解説していきます。
FIT(固定価格買取制度)期間が満了になること
卒FITとは、FIT制度(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)の期間が満了になることです。
FIT制度は再生可能エネルギーの普及を目的に2012年から始まりましたが、前身である『太陽光余剰電力買取制度』が始まったのは2009年。
電力会社は、太陽光発電で作られた電気のうち自家で消費する分を差し引いた電力(余剰電力)を買い取ってきました。
住宅用太陽光発電の余剰電力の買取期間は10年間とされていますので、制度を利用してきた人が2019年から買取期間を終えることとなっています。
固定価格買取制度とは?
固定価格買取制度とは、再生可能エネルギーで発電した電気を、
電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。
同庁によると、住宅の屋根で発電するような10kW未満の太陽光の場合は、余剰電力だけが買取対象。
つまり、発電した全ての電気を買い取ってもらうことはできません。
ちなみに、買い取ってもらえるのは太陽光だけでなく、『風力』『水力』『地熱』『バイオマス』で発電した電力も対象です。
また、電気の買取にかかる費用は『再エネ賦課金』でまかなわれています。
ちなみに再エネ賦課金とは、再生可能エネルギーの買取費用に充てられるお金で、電気使用量に応じて金額が変わります。単価は毎年度、経済産業大臣によって定められます。
期間満了時期の調べ方
自分の固定価格買取期間がいつ満了となるかは、買取開始時期を確認することで分かります。
売電している電力会社との契約書や案内書、検診票などを確認してみましょう。
新築と同時に太陽光パネルを使用した場合は、住み始めた時期から推測することもできますね。
また、買取期間満了のだいたい6〜4ヶ月前には、売電している電力会社から通知が届くことになっています。
私の場合、新築当時の契約書で買取開始時期を確認したら『2012年12月』と書いていて、まだ通知は届いていません。
卒FIT後何もしないとどうなる?
卒FIT後は、住宅用太陽光発電設備の管理や、発電された電気をどうするかは自己管理することになります。
卒FIT後に何もしないと、
- 継続して新しい単価で買取が行われる
- 無料で引き取られ
どちらかのケースに分かれます。
どちらになるかは、自動契約をしているかどうかで変わりますので、自分の契約内容を確認しましょう。
自動契約をしている場合は、同じ電力会社の新しい単価での買取が行われます。
一方、自動契約ではない場合は、別に契約を結ばない限り買取者が不在となってしまうため、一般送配電事業者(大手電力会社)に無償で引き受けられることになります。
せっかく発電した電気を無償で引き受けられてしまうのはもったいないですよね。
卒FIT後は契約がどうなるのか、確認しておきましょう。
一般送配電事業者とは、東京電力や関西電力などの経済産業大臣から一般送配電事業を営む許可を受けた事業者のことを指します
買取終了後、売電収入はどれくらい下がる?
自動契約となっている場合は、新しい単価での継続買取となりますが、買取金額は大幅に変わります。
試しに、私の例でどうなるかシミュレーションしてみました。
まずは、買取価格は
- 現在の買取価格:42円(1kWh、買取業者:東北電力)
- FIT後の買取価格:9円(1kWh、買取業者:東北電力『シンプル買取』)
となり、1kWhあたり33円下がります。
私の2021年1〜12月の売電量は2,691kWhでしたので、それぞれ金額に直してみると、
| 年間 | 月平均 | |
| 現在 | 113,022円 | 9,418円 |
| 卒FIT後 | 24,219円 | 2,018円 |
| 差額 | −88,803円 | −7400円 |
年間で90,000円弱、月平均でも7,000円以上売電収入が下がることになります。
卒FIT後、余った電気の使い道は?
卒FIT後の余剰電力の使い道は大きく
- 大手電力会社に継続して売電
- 家庭用蓄電池や電気自動車(EV)に溜めて使う
- 買い取ってもらう会社を変える
の3つです。
それぞれ、メリットとデメリットを解説しますので、自分に合った使い道を検討しましょう。
大手電力会社に継続して売電
今、売電している電力会社との契約を継続する方法の一番のメリットとして、手間が少ないことが挙げられます。
もし、契約が自動更新になっていれば、更新手続きの必要はありません。
また、これまで取引をしてきたという安心感もメリットの一つでしょう。
デメリットは、買取金額が大幅に安くなること。
各電力会社の基本的な買取価格を地域ごとにまとめてみましたが、各社とも複数の買取プランがあったり、条件によって単価が変わったりしますので、詳細はWebサイトを確認してくださいね。
| 電力会社 | 買取価格 | プラン名 |
| 北海道電力 | 8円/kWh | 買取プラン |
| 東北電力 | 9円/kWh | シンプル買取 |
| 東京電力 | 8.5円/kWh | 再エネ買取標準プラン |
| 北陸電力 | 8円/kWh | かんたん固定単価プラン |
| 中部電力 | 8円/kWh | プレミアムプラン |
| 関西電力 | 8円/kWh | ー |
| 中国電力 | 7.15円/kWh | ー |
| 四国電力 | 7円/kWh | ー |
| 九州電力 | 7円/kWh | ー |
| 沖縄電力 | 7.7円/kWh | ー |
家庭用蓄電池や電気自動車(EV)に溜めて使う
2つ目は、自家発電した電気を家庭用蓄電池や電気自動車(EV)などに充電して、自宅で消費する方法。
溜めた電気は、主に夜間電力や自動車の駆動力として使用できます。
メリットは、自宅で発電した電気を無駄なく使うことで電力会社から買う電気量が少なくなるため、毎月の電気代が安くなるという点です。
また、台風などの自然災害時に停電となった場合、非常用電源として使用することができるのも、大きなメリットの一つと言えるでしょう。
注意点は、大きな導入コストがかかること。
容量にもよりますが100万円前後の出費のほか、蓄電池であれば屋外に設置するスペースが必要です。
また、自宅に合った蓄電池を検討する時間もコストといえます。
自治体によっては補助金の交付を受けられる可能性もありますので、覚えておきましょう。
必要な蓄電池容量の計算式
家庭用蓄電池を選ぶポイントの一つに、容量(溜めておける電気の量)があります。
自分に合った容量の計算方法を紹介します。
まずは、自分の家ではどれくらいの電力を消費しているのかを知っておきましょう。
もちろん、モデルや条件によって変わりますが、一般的な電化製品の消費電力を紹介します。
| 電化製品 | 消費電力 |
| 電子レンジ | 1,300W |
| エアコン(10畳用) | 700W |
| IH調理器(中) | 700W |
| 洗濯機(8kg) | 600W |
| 冷蔵庫(40L) | 190W |
| テレビ | 150W |
| 照明 | 100W |
必要な電気容量は、
[surfing_su_note_ex note_color=”#F8F8FF”]電化製品の消費電力(W)×時間(h)
[/surfing_su_note_ex]で計算できます。
例えば、エアコン(700W)とテレビ(150W)、照明(100W)を5時間使用したとすると、
[surfing_su_note_ex note_color=”#F8F8FF”](700+150+100)×5=4,750Wh(4.75kWh)
[/surfing_su_note_ex]となり、4.75kWhが必要な容量となります。
4人家族の1日の電気使用量は約18.5kWhと言われています。
また、停電時に必要最低限な容量は4kWhという情報もありますので、自分がどのような目的で蓄電池を使用するのかを考えながら、必要容量を計算してみましょう。
買い取ってもらう会社を変える
3つ目の方法は、買い取ってもらう会社を変えること。
大手電力会社ではなく、新電力会社と契約することも、選択肢の一つです。
新電力会社とは電力自由化に伴って設立された小売電気事業者のこと。
またまた私の例にはなりますが、東北エリアでサービスを提供している会社の中でも、条件によって大手電力会社の買取金額である9円よりも高い価格で買取ってくれる会社をピックアップしました。(買取価格は円/kWh)
| 会社名 | 買取価格 | 記事 |
| 丸紅新電力 | 14 | SHARPプラン 蓄電池プレミアム |
| ヘーベル電気 | 12 | 旭化成ホームズグループで蓄電池も購入・設置 |
| SAMRT TECH | 11.5 | 申し込み多数のため、新規受付停止中 |
| idemitsuでんき | 11.5 | idemitsuでんきを同時に契約 |
| ENEOS | 11 | |
| 坊っちゃん電力 | 11 | スタンダード+プラン |
| エバーグリーン・リテイリング | 10.5 | プレミアムプラン |
| JAでんき | 10 | JAでんき使用 |
2022年4月現在の情報です。
日本の大手企業も電気事業に参入していて、さまざまな条件により大手電力会社よりも高い金額で買い取ってくれます。
自分に合った買取会社を探しましょう。
余った電気の使い道をシミュレーション!
具体的に、余剰電力の使い道をシミュレーションしてみましょう。
条件は以下のとおりです。
| ① | 太陽光発電システム容量 | 4kW | |
| ② | 年間発電量 | 4,000kWh | 容量の1000倍 |
| ③ | 年間電力消費量 | 5,000kWh | |
| ④ | 買取価格 | 11円/kWh | ENEOS |
| ⑤ | 電気料金単価 | 24.1円/kWh |
この条件で、
[surfing_su_note_ex note_color=”#F8F8FF”]- 蓄電池を導入せず、売電:ENEOS / 買電:東北電力(継続)
- 蓄電池を導入して、余剰電力は自家消費、不足分を東北電力から購入
の2パターンで比較します。
自家消費率は、資源エネルギー庁が公表しているデータ(地域活用要件について)から、30%として計算します。
まずは、『1.蓄電池を導入せず、売電:ENEOS / 買電:東北電力(継続)』のパターンです。
【年間の買電料金】
③5,000kWh×⑤24.1円=約12万円
【自家消費による買電の削減】
③5,000kWh×30%×⑤24.1円=約3.6万円
【売電収入】
(②4000kWh−③5,000kWh×30%)×④11円=約2.8万円
買電料金から自家消費分と売電分を差し引くと、約5.6万円を支払うことになります。
次に『2.蓄電池を導入して、余剰電力は自家消費、不足分を東北電力から購入』のパターンを見てみましょう。
今回の自家消費率は、蓄電池導入により70%と想定して計算します。
【年間の買電料金】
③5,000kWh×⑤24.1円=約12万円
【自家消費による買電の削減】
③5,000kWh×70%×⑤24.1円=約8.4万円
【売電収入】
(②4000kWh−③5,000kWh×70%)×④11円=約0.5万円
こちらのパターンでは支払額が3.1万円となりました。
今回のシミュレーションでは、『2.蓄電池を導入して、余剰電力は自家消費、不足分を東北電力から購入』の方が、年間の支払い金額で2.5万円安くなりました。
『自家消費による買電の削減』の違いが、結果に大きく影響していることがわかります。
ただし、このシミュレーションには蓄電池購入や設置工事の費用は含まれていません。
蓄電池購入の費用は、使用するモデルや容量にもよりますし、どれくらい補助金を活用できるかにもよって変わります。
また、太陽光発電システムには、発電した電気を家庭などで使用できる電気に変換するためのパワーコンディショナという装置がついています。
パワーコンディショナの保証期間は、多くのメーカーで10年程度の場合がほとんどで、ちょうど卒FITのタイミングが交換時期と重なる場合も。
条件によってコストは変わりますので、自分のケースに当てはめて考えてみましょう。
まとめ
卒FITを迎えるにあたり、余剰電力の使い道について解説してきました。
さらに家計への負担を軽くするためには、買電プランも見直しの必要があるかもしれません。
近年は、新電力と呼ばれる会社が色々な買電プランを出していますので、お住まいの地域によっては大手電力会社からの購入よりも安くなる可能性も。
自分の状況や用途に合わせて、上手に卒FITを迎えましょうね!
| この記事の監修:嵯峨根 拓未 所有資格:宅地建物取引士 |