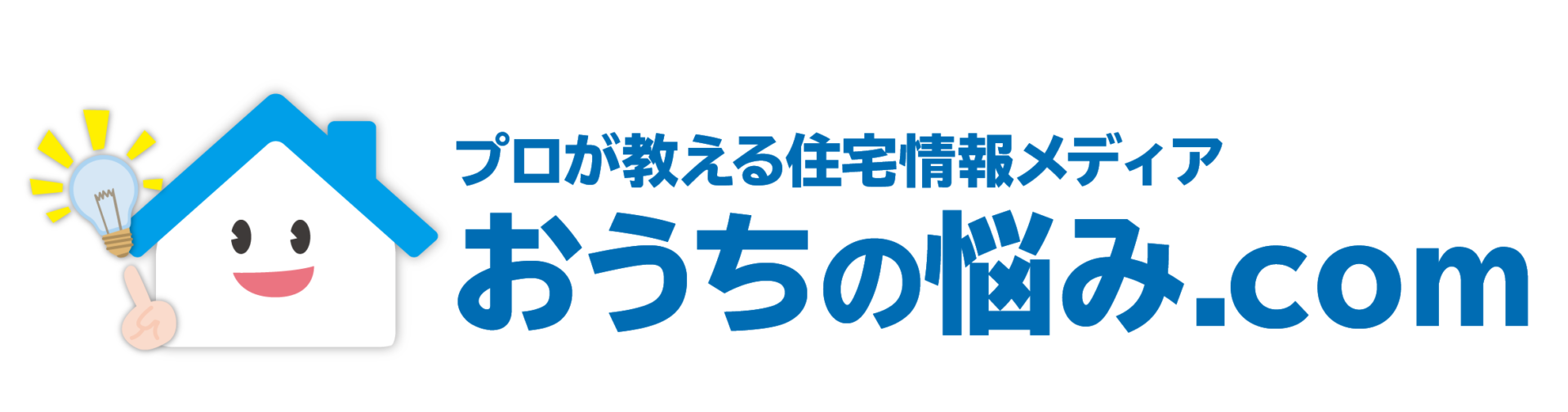憧れのマイホームを建てる時、代表的なコストである固定資産税への理解はとても大切です。
固定資産税を調べたことがある方は、「広さによって固定資産税が高くなる」などの情報に触れることもあるかもしれません。
今回は、建物や敷地の広さによって固定資産税額が変わる仕組みや、固定資産税を抑えるための方法を紹介します。
長い期間支払う固定資産税ですので、しっかりと理解を深めておきましょう。
固定資産税とは

固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している人に課税される税金です。
毎年1月1日に、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が対象となります。
国に納付する国税ではなく市町村に納める地方税のため、納税通知書は固定資産がある市町村から届きます。
固定資産税の課税額を計算する式は以下のとおり。
[surfing_su_note_ex note_color=”#F8F8FF”]固定資産税=課税標準額×1.4%
[/surfing_su_note_ex]課税標準額とは、税金の基礎となる金額で、固定資産税評価額をもとに算出されます。
課税標準額に乗じている1.4%は一般的な税率です。
市町村によっては異なる税率を設けているところもありますので、詳しくは総務省のホームページで確認しましょう。
参考:総務省ホームページ
固定資産税評価額とは
固定資産税評価額とは、固定資産税を決めるために必要な課税標準額を算出するためのもの。
固定資産の評価は、調査員などが直接住宅や土地などの固定資産を調査した結果と固定資産評価基準によって、決定します。
固定資産税評価額がそのまま課税標準額になる場合もありますが、軽減措置などが反映されるケースがありますので、必ずしも同じ金額になるわけではありません。
少し複雑なので、まとめると以下のとおりです。
- 固定資産を評価し、固定資産税評価額が決定
- 固定資産税評価額をもとに、課税標準額を算出
- 課税標準額に税率をかけて、固定資産税を算出
固定資産税評価額がそのまま課税標準額になるわけではありませんので気を付けましょう。
金額の目安と計算方法は?
固定資産を持っている人は、どれくらいの金額を支払っているのでしょうか?
ここでは、固定資産税額の目安と基本的な計算方法を紹介します。
固定資産税評価額は、3年ごとに行われる評価見直しによって変わりますので時価といえるかもしれません。
また、建物のグレードなどによっても変わりますので、あくまで基本的な情報として覚えておきましょう。
建物の場合
建物の固定資産税額の基本的な計算式は以下のとおりです。
[surfing_su_note_ex note_color=”#F8F8FF”]固定資産税額=固定資産税評価額×軽減措置×1.4%
[/surfing_su_note_ex]固定資産税評価額は建物にどの程度の価値があるかを評価した金額で、一般的には取得金額の50〜60%程度といわれています。
ただし、使用している建材や木造などの構造、 設備のグレードによって評価額は変わりますので、あくまで目安として覚えておいてくださいね。
軽減措置とは、新築住宅の場合に120㎡までの固定資産税が減税される制度のこと。
詳細は以下の表のとおりです。
| 種類 | 金額 | 減額措置を受けられる期間(※) |
| 戸建て | 1/2 | 3年間 |
| マンション | 1/2 | 5年間 |
※長期優良住宅の場合は、戸建て5年間、マンション7年間
ここでは、
- 延床面積150㎡
- 建物購入金額:2,000万円
- 固定資産税評価額:購入金額の60%
- 新築戸建て
とした場合の、固定資産税の金額を算出してみました。
[surfing_su_note_ex note_color=”#F8F8FF”]- 120㎡までの部分=2,000万円×60%×(120㎡/150㎡)×1/2×1.4%=67,200円
- 121㎡を超える部分=2,000万円×60%×(30㎡/150㎡)×1.4%=33,600円
- 67,200円+33,600円=100,800円
つまり、建物の場合は「120㎡までの部分は固定資産税が一定期間安くなる」ということになります。
この減税措置は期限付きですので、長い期間住むことを考えると受けられるメリットは限定的といえますね。
減税のためとはいえ、延床面積を抑えることが本当に快適な暮らしにつながるのか、よく検討しましょう。
土地の場合
土地の場合の基本的な固定資産税も、建物の場合と同じ方法で算出できます。
計算式は以下のとおり。
[surfing_su_note_ex note_color=”#F8F8FF”]固定資産税額=固定資産税評価額×軽減措置×1.4%
[/surfing_su_note_ex]住宅が建てられる宅地の固定資産税評価額は、地価公示価格の7割をめどに設定されています。
地価公示価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」で調べられますよ。
参考:国土交通省「不動産情報ライブラリ」
ここでは、1,500万円の土地を例にして、基本的な固定資産税の金額を計算してみましょう。
[surfing_su_note_ex note_color=”#F8F8FF”]147,000円=(1,500万円×70%)×1.4%
[/surfing_su_note_ex]この金額に減税措置が反映されて、実際に支払う固定資産税の金額になります。
減額措置については、後ほど詳しく解説します。
住宅用地の特例措置

居住用の建物が建っている土地は住宅用地と呼ばれ、固定資産税が減額される特例措置を受けられます。
具体的には、住宅一戸あたり200㎡までは1/6、201㎡以上の部分は1/3に減額。
住宅用地とは、一戸建てやアパート等に加え、一体となっている庭や駐車場に使用されている土地のことです。
店舗や事務所などは、住宅用地の条件に該当しませんので注意しましょう。
ここでは、住宅用地の特例措置について詳しく解説します。
課税標準額の減税
住宅用地は、『小規模住宅用地』と『一般住宅用地』に分けられます。
小規模住宅用地とは200㎡(約60坪)まで、一般住宅用地とは201㎡以上の土地のこと。
敷地面積によって、以下の表のとおり対象となる軽減措置が変わりますので注意してくださいね。
| 特例措置 | 適用部分 | |
| 小規模住宅用地 | 1/6 | 200㎡まで部分 |
| 一般住宅用地 | 1/3 | 201㎡以上の部分 |
土地が200㎡までの場合
200㎡(約60坪)までの土地は小規模住宅用地とされ、固定資産税が1/6になる減税措置が受けられます。
例えば、1,500万円で購入した150㎡の土地に対する固定資産税を計算する方法は、以下のとおり。
[surfing_su_note_ex note_color=”#F8F8FF”]24,500円=1,500万円×70%×1/6×1.4%
[/surfing_su_note_ex]もし201㎡以上の土地でも、201㎡未満の部分に対しては小規模住宅用地の減税措置が適用されますので安心してください。
土地が201㎡以上の場合
201㎡以上の土地は一般住宅用地とされ、減税措置は1/3になります。
例えば2,000万円で購入した250㎡の土地の場合で考えてみましょう。
200㎡までの部分に対しては1/6の措置を受けられますので、計算式は以下のとおりです。
[surfing_su_note_ex note_color=”#F8F8FF”]- 200㎡まで=2,000万円×70%×1.4%×(200㎡/300㎡×1/6)=約2.2万円
- 201㎡以上=2,000万円×70%×1.4×(50㎡/300㎡×1/3)=約1.1万円
- 約2.2万円+約1.1万円=約3.3万円
複雑な計算が必要ですので、不安な時はお住まいの自治体に問い合わせると教えてくれますよ。
住宅用地なら都市計画税の減税も
居住用の建物が建っている住宅用地なら、都市計画税が減税される措置も。
都市計画税とは、毎年1月1日時点で都市計画区域内に固定資産を所有している人に課税される税金で、道路や下水道などを整備する財源として活用されます。
都市計画税は以下の式で計算できますよ。
[surfing_su_note_ex note_color=”#F8F8FF”]都市計画税=課税標準額×制限税率(0.3%)
[/surfing_su_note_ex]都市計画税の税率は、0.3%を上限とした制限税率ですので、お住まいの市区町村の税率を調べてみましょう。
都市計画税の軽減措置も、敷地面積によって内容が変わりますので詳しくみてみましょう。
土地が200㎡までの場合
土地が200㎡までの場合、都市計画税が1/3になる措置が受けられます。
具体的な計算式は、以下のとおりです。
[surfing_su_note_ex note_color=”#F8F8FF”]都市計画税=課税標準額×0.3%×1/3
[/surfing_su_note_ex]201㎡以上の土地でも、土地の固定資産税と同じように200㎡までの土地は1/3になりますよ。
土地が201㎡以上の場合
201㎡以上の部分は、都市計画税が2/3になります。
まとめると以下の表のとおりです。
| 特例措置 | 適用部分 | |
| 小規模住宅用地 | 1/3 | 200㎡まで部分 |
| 一般住宅用地 | 2/3 | 201㎡以上の部分 |
固定資産税と同じように、201㎡以上の土地でも200㎡までは1/3、201㎡を超えた部分は2/3の特例措置を受けられます。
固定資産税が上がるケースに注意

ここまでの解説を踏まえ、どのようなケースだと固定資産税が上がるのかを紹介します。
固定資産税額を算出するための評価額の変化や、減税措置を受けられなくなることで支払額がいくらになるのかが変わることも。
支払う固定資産税を上手に抑えることは、家計への負担を減らすことにつながりますよ。
ハウスメーカーによっては工法により評価額が上がることも
ハウスメーカー独自の工法によっては、固定資産税評価額が上がるケースがあります。
固定資産税の金額は以下の計算式で算出しますので、固定資産税評価額が上がると、計算結果である固定資産税の金額が上がるという仕組みです。
[surfing_su_note_ex note_color=”#F8F8FF”]固定資産税=課税標準額(=固定資産税評価額×減税措置)×1.4%
[/surfing_su_note_ex]注文住宅のランキングに登場するような大手ハウスメーカーには、売りにしている構造や資材、工事方法がありますよね。
それらの技術などが、建物の評価を上げてしまうことになる可能性があるのです。
もしハウスメーカーが売りにしている技術などにこだわりがないのであれば、無料で見学できるモデルハウスもありますので、複数のハウスメーカーを調べてみましょう。
住宅を取り壊した場合
住宅を取り壊した場合、建物に対する固定資産税は不要になりますが、土地との割合によっては支払う固定資産税が上がるケースも。
理由は、住宅用地としての減税措置を受けられなくなるためです。
居住用の建築物が建てられている土地は、200㎡までの小規模住宅用地なら1/6、201㎡以上の一般住宅用地なら1/3になる減税措置を受けています。
住宅を取り壊すことで住宅用地から除外されると、住宅用地としての減税措置を受けられなくなってしまい、土地に対する固定資産税の支払額が高くなるというわけです。
固定資産税が高くなるというよりは、減税措置が受けられなくなるといった方が正しいのですが、結果として支払う固定資産税が高くなりますので気を付けましょう。
住宅用地かどうかは、固定資産税だけでなく都市計画税にも影響しますので注意してくださいね。
空き家として放置している場合
使わなくなった建物を空き家として放置していると、支払う固定資産税の金額が高くなるケースがあります。
2015年に、空き家の増加による周囲の生活環境の悪化や家屋の崩壊、火災のリスクを懸念し、『空き家等対策の推進に関する特別措置法』が施行されました。
この法律により、市町村は管理状態が不十分な空き家を『特定空き家』に指定できるように。
特定空き家に指定されると、市町村から空き家の所有者に対して『助言・指導』が行われます。
助言・指導により状況が改善されない場合は、『勧告』が行われます。
勧告が行われると住宅用地から除外され、土地の固定資産税に対する住宅用地の特例措置を受けられなくなってしまい、その結果支払う固定資産税が高くなるというわけです。
空き家の処分には解体費用や相続税がかかることで頭を悩ませるかもしれませんが、放置せず早めの処分を検討しましょう。
まとめ

今回は建物や土地の広さによって、固定資産税の支払額が変わる仕組みを解説してきました。
固定資産税額の決定には、様々な条件による減税措置が関係しています。
また、土地も建物も面積が小さい方が大きな減税措置を受けられることが分かりましたね。
ただし、減税措置には期間限定のものもあります。
減税するために広さを抑えることは、本当に快適な暮らしといえるのかよく検討してくださいね。
固定資産税などを含め、くれぐれも、マイホーム作りは慎重に検討してください。
[surfing_su_note_ex note_color=”#F8F8FF”] [/surfing_su_note_ex]
| この記事の監修:嵯峨根 拓未
所有資格:二級建築士、宅地建物取引士 |